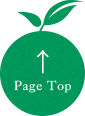内科・皮膚科疾患のお話
Blog
Blog
■とびひとは?
とびひの正式な病名は【伝染性膿痂疹】といいます。細菌が皮膚に感染することで発症し人にうつる病気です。
掻きむしった手を介して、水ぶくれ(水疱)があっという間に全身へ広がる様子が、火事の火の粉が飛び火することに似ているため【とびひ】と呼ばれています。
■どんな病気?
とびひには水ぶくれができるもの(水疱性膿痂疹)とかさぶたができるもの(痂皮性膿痂疹)の2種類があり、それぞれの特徴は次の通りです。
アトピー性皮膚炎の患者さんは皮膚のバリア機能が低下しており、とびひにかかりやすいので注意しましょう。
・水ぶくれができるもの:水疱性膿痂疹
皮膚にできた水ぶくれがだんだん膿を持つようになり、やがて破れると皮膚がめくれてただれてしまいます。
かゆみがあり、患部を掻いた手で身体の他の部分を触ると症状がありこちに広がってしまいます。
とびひの多くはこのタイプで、黄色ブドウ球菌が原因です。
・かさぶたができるもの:痂皮性膿痂疹
皮膚の一部に膿を持った水ぶくれ(膿疱)ができ厚いかさぶたになります。炎症が強く、リンパ節が腫れたり、発熱やのどの痛みを伴うこともあります。
主に化膿レンサ球菌が原因となりますが、黄色ブドウ球菌も同時に感染していることが多いです。
■どのような治療方法?
とびひには、原因となる細菌を退治する治療を行います。かゆみが強い場合はかゆみを抑える治療も行います。
とびひはひどくならないうちに治療を始めるとより早く治すことができます。気になる症状があれば、早めに皮膚科や小児科を受診しましょう。
■日常生活でこころがけること
①患部を掻いたり、いじったりしない
とびひは患部を触った手を介して症状が身体のあちこちに広がることがあります。
患部に触らないように注意し、引っかかないよう爪を短めに切るようにしましょう。
②皮膚を清潔に保つ
原因となる細菌を減らすため、入浴して皮膚を清潔に保つことが大切です。患部はこすらず、石鹸をよく泡立て、泡で丁寧に洗い、その後はシャワーでよく洗い流しましょう。また湯舟につかってよいかは医師と相談しましょう。
➂タオルや衣類は共有しない
タオルや衣類を介してとびひがうつることもあります。共用しないようにしましょう。
■とびひQ&A
Q.薬はいつまでつづけたらよいですか?
A.とびひは症状が良くなっても、原因となる細菌が残っていることがあります。自己判断で薬をやめずに医師の指示に従いましょう。
Q.通園、通学はやめた方がいいですか?
A.出席停止が義務付けられた病気ではありませんが、とびひの状態や、通園・通学先の規則にもよりますので、医師や担任の先生、保育士さんに相談しましょう。
また、通園・通学をする場合、他人にうつさないよう、患部をガーゼや包帯で覆いましょう。
Q.プールに入っても大丈夫ですか?
A.プールに入ると症状がひどくなったり、他の人にうつしてしまうこともあるので治るまで控えましょう。またプールに入る時期については、医師や担任の穿刺江、保育士さんに相談しましょう。
何かご不明点ございましたら当院までお問い合わせください。
東京メトロ東西線・葛西駅西口より徒歩5分、葛西内科皮膚科クリニックです。