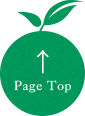内科・皮膚科疾患のお話
Blog
Blog
■脂質異常症とは?
脂質異常症とは、コレステロールや中性脂肪などの脂質代謝に異常が発生している状態のことです。
一般的にはLDL(悪玉)コレステロールや血液中の中性脂肪が必要上に増えるか、HDL(善玉)コレステロールが減った状態のことを表します。
■【コレステロール】と【中性脂肪(トリグリセライド)】とは?
コレステロールや中性脂肪は体内にある脂質(あぶら)の一種です。悪者扱いされることがありますが、どちらも私たちの身体になくてはならない物質です。
脂質は、水となじみやすいタンパク質と結びついて(リポ蛋白)血液中に存在し全身に運ばれます。
【コレステロール】
体の中のコレステロールには、
①細胞膜の主な材料
②副腎皮質ホルモンや性ホルモンの原料
➂脂肪の消化に必要な胆汁の主成分になる
などの働きがあります。コレステロールの約2/3は体内(主に肝臓)でつくられ、約1/3は食事からとられています。
血液中のコレステロールは、どのリポ蛋白に含まれているかによりLDLコレステロールとHDLコレステロールに分けられます。
☆LDL(悪玉)コレステロール
肝臓から体内の各臓器へコレステロールを運びます。増えすぎると動脈硬化の原因になります。
☆HDL(善玉)コレステロール
血管や体内にたまった余分なコレステロールを回収し肝臓に戻します。動脈硬化を防ぐ働きをします。
【中性脂肪】
中性脂肪(トリグリセライド)は、私たちが活動するときのエネルギー源になるほか、体温を保ったり、外部の衝撃から内臓を守る働きがあります。
主に糖分や脂肪酸を材料として肝臓で作られ、肝臓や脂肪組織に蓄えられます。アルコールはこれを促進します。血液中の中性脂肪(トリグリセライド)が増えすぎるとHDLコレステロールは逆に減少し、動脈硬化が促進されます。
■コレステロール値が高い状態が続くと
☆脂質異常症と動脈硬化
血液中のLDLコレステロールや中性脂肪(トリグリセライド)が増えすぎたり、HDLコレステロールが少なくなる状態を『脂質異常症』といいます。
LDLコレステロールが高いと血管の壁に滲み出て溜まり、血管の内側が狭く硬くなり、血液が流れにくくなります。この状態を『動脈硬化』といいます。
脂質異常症も動脈硬化も、痛みやかゆみなどの自覚症状のないことが多いため放置しがちです。
☆動脈硬化により起こる病気(動脈硬化性疾患)
動脈硬化が進むと、血管の内側がさらに狭くなります。脳や心臓の血流が悪くなると、血管の壁が破れて血栓ができ血管が詰まったりします。すると下記のような病気を発症する危険性が高くなります。
脳▶脳梗塞
心臓▶狭心症、心筋梗塞
手足など▶末梢動脈疾患(PAD)
■コレステロールや中性脂肪が高くなる原因
☆生活習慣の乱れ
脂質異常症の多くは生活習慣の乱れが原因です。最近は子供でも食生活の乱れや運動不足によって脂質異常症が増えています。
・肥満 ・運動不足 ・ストレス、疲れ ・睡眠不足、生活リズムの乱れ
・食べ過ぎ、偏食、脂肪・糖分の取りすぎ、お酒の飲みすぎ など
☆体質(遺伝性)
遺伝的な要因が原因になることがあります(家族性高コレステロール血症)。若いうちから発症すると、若年性の心筋梗塞などが起こりやすくなります。
☆喫煙
煙草の煙にはHDLコレステロールを下げる有害物質が含まれています。
☆そのほかの影響
糖尿病、甲状腺機能低下症、腎不全などの病気が原因になる事もあります。
また加齢や閉経によりLDLコレステロールが高くなることもあります。
■脂質異常症の診断とタイプ
脂質異常症は、血液検査で調べることができます。血液中のそれぞれの脂質、
・LDLコレステロール
・HDLコレステロール
・中性脂肪及びNon-HDLコレステロール
の値によって下記の4つのタイプに分けられます。
☆LDLコレステロール
140mg/dL以上 → 高LDLコレステロール血症
120~139mg/dL → 境界域高いLDLコレステロール血症
☆HDLコレステロール血症
40mg/dL → 低HDLコレステロール血症
☆中性脂肪
150mg/dL → 高中性脂肪血症
☆Non-HDLコレステロール血症
170mg/dL → 高non-HDLコレステロール血症
150~169mg/dL → 境界域高non-HDLコレステロール血症
■治療の目的と内容
脂質異常症は、長期間にわたり治療を続けることが大切です。これまでの生活習慣で改善すべき点や、病気のことをよく理解しましょう。
☆治療の目的
治療の目的は、血液中の脂質を良好な値にコントロールして、動脈硬化や動脈硬化により起こる病気(心筋梗塞などの動脈硬化性疾患)を予防することです。
動脈硬化性疾患は、脂質異常だけではなく、次にあげるようなリスクの数が多いほど、発症する危険が高くなると考えられます。
・肥満 ・メタボリックシンドローム※ ・喫煙 ・慢性腎臓病(CKD) ・糖尿病
・高血圧 ・高尿酸血症 …
動脈硬化性疾患を予防するためには、脂質異常症の治療と合わせてこれらのリスクをケアすることも大切です。
※メタボリックシンドロームとは
メタボリックシンドロームは動脈硬化性疾患の原因として注目されています。内臓脂肪型肥満に加えて、脂質、血圧、血糖のうち2つ以上の項目が診断基準に当てはまる状態をメタボリックシンドロームといいます。
☆治療の内容
これまでの生活習慣の改善を行います。
食生活を変えたり、運動を始めることでLDLコレステロールや中性脂肪の値を正常な状態に戻します。生活習慣の改善を行っても脂質の値が改善しない場合は、お薬による治療が検討されます。ただし、病状によっては 早い時期からお薬による治療を始めることがあります。
■生活習慣の改善
長年続けてきた習慣を変えるのは簡単な事ではありませんが、できるところから少しずつ着実に変えていく事が大切です。
また頑張りすぎてストレスを溜めないように、長く続けられる方法を見つけましょう。
生活習慣の予防や健康づくりにもつながるので家族みんなで取り組むのも一つの方法です。
☆何を改善するの?
・食生活を変える
食生活の乱れは、脂質バランスの乱れを招く大きな原因のひとつです。食生活を見直し、食事のバランスを整えましょう。
※次回、別途記事を掲載予定です。
・運動を始める
脂質異常症の予防や治療では食生活の改善とともに運動不足を解消することが重要です。運動が苦手な方も日々の生活の中でこまめに身体を動かすよう心掛け、習慣にしていきましょう。
《運動の効用》
・基礎代謝のアップ ・皮下脂肪や内臓脂肪を減らし、蓄積されるのを防ぐ
・中性脂肪が減り、HDLコレステロールが増える ・インスリン抵抗性の改善
・生活習慣病の予防や治療 ・ストレス解消 ・体力の向上
《運動のポイント》
・始める前に、必ず医師のチェックを受けましょう
・有酸素運動を1日30分以上、週3回(できれば毎日)続けましょう
・少し汗ばむくらいの運動を目安に
・ウォーミングアップ、こまめな水分補給を忘れずに
・体調がすぐれないときは、無理せず休むようにしましょう
・無理な力がかかったり、競技性の高い運動は避けましょう
☆その他の改善点
・禁煙する
喫煙は、動脈硬化や心筋梗塞の危険因子の一つです。できるだけ早く禁煙しましょう
自分の意思だけで禁煙するのが難しい場合などは、禁煙外来で治療を受けるという方法もあります。
他の人が吸ったたばこの煙を吸い込む受動喫煙も冠動脈疾患、脳卒中の危険性を高めるため、注意が必要です。
・体重をコントロールする
肥満(特に内臓肥満)があると、脂質や糖の代謝異常を起こしやすくなります。体重をきちんとコントロールしましょう。
体格指数(BMI)=体重(Kg)÷身長(m)÷身長(m)
※BMI:25以上→肥満、18.5以上25未満→適正体重
・ストレス・疲れを解消する
ストレスにさらされていると、心身の緊張が高まり、脂質異常症や動脈硬化の悪化につながります。体を動かす、働きすぎない、ゆっくりお風呂に入る、など自分に合った解消方法を見つけましょう
・生活リズムを整える
睡眠不足や生活リズムの乱れは脂質代謝に悪い影響を与えます。十分な睡眠、規則正しい生活リズムを心がけましょう。
何かご不明点ございましたら当院までお問い合わせください。
東京メトロ東西線・葛西駅西口より徒歩5分、葛西内科皮膚科クリニックです。