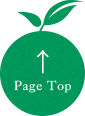今年の4月頃から、子供を中心に感染し激しいせきが続く「百日咳」の流行が続いていています。この記事ではそんな百日咳について解説していきます。
🎵病態
百日咳は、百日咳菌という細菌によって引き起こされる、非常に感染力の強い呼吸器感染症です。その特徴的な症状は、激しい咳が連続して起こり、息を吸う時に「ヒュー」という笛のような音が出ることです。しかし、この典型的な症状が現れないこともあり、特に乳幼児や高齢者では注意が必要です。
百日咳は、その経過によって大きく3つの時期に分けられます。
- カタル期(約1~2週間)
- 痙咳期(約2~8週間)
- 回復期(数週間~数ヶ月)
百日咳菌にはいくつかの菌株が存在しますが、病態に大きな違いは見られないとされています。
🎵原因
百日咳の主な原因菌は、グラム陰性桿菌である百日咳菌です。感染経路は、患者の咳やくしゃみなどによって空気中に放出された菌を吸い込むことによる飛沫感染です。非常に感染力が強く、家族内感染率は80%にも及ぶとされています。
百日咳は、世界中で発生が見られますが、ワクチン接種の普及により先進国では発生頻度が低下しています。しかし、ワクチン接種を受けていない乳幼児や、ワクチン効果が減弱した学童期以降の年齢層での発生も依然として見られます。近年、成人における百日咳の増加も報告されており、長引く咳の原因として考慮する必要があります。
🎵症状(自覚・他覚症状)
百日咳の症状は、時期によって変化します。
■カタル期(1~2週間)
- 自覚症状: 鼻水、軽い咳、喉の痛み、微熱など、風邪と区別しにくい症状が現れます。
- 他覚症状: 鼻汁、咽頭の発赤などが見られることがあります。
この時期はまだ百日咳と気づきにくく、感染力が最も強い時期でもあります。
■痙咳期(約2~8週間)
- 自覚症状: 激しい咳が連続して起こり、息苦しさを感じます。咳の後に「ヒュー」という音が出ることがあります。夜間に症状が悪化しやすい傾向があります。
- 他覚症状: 連続する咳込みにより、顔面紅潮、チアノーゼ、眼球結膜出血が見られることがあります。咳の終わりには嘔吐を伴うこともあります。乳幼児では、呼吸困難や無呼吸発作を引き起こすこともあり、注意が必要です。
この時期が百日咳の最も特徴的な時期です。
■回復期(数週間~数ヶ月)
- 自覚症状: 咳の回数や程度は徐々に軽減しますが、刺激に敏感になり、しばらくの間は咳が出やすい状態が続きます。
- 他覚症状: 徐々に咳の頻度が減っていきます。
他の呼吸器感染症にかかりやすくなることもあります。
🎵検査
百日咳の診断には、主に以下の検査が行われます。
- 鼻咽腔ぬぐい液検査: 細い綿棒のようなもので鼻の奥の粘液を採取し、百日咳菌の培養検査やPCR検査を行います。培養検査には時間がかかりますが、菌の存在を直接確認できます。PCR検査は、菌の遺伝子を検出するため、比較的早期に結果が得られます。
- 血液検査: 白血球数、特にリンパ球の増加が見られることがあります。炎症反応を示すCRPなどの値も上昇することがあります。
- 胸部X線検査: 肺炎などの合併症の有無を確認するために行われることがあります。
🎵治療(生活習慣・薬物・手術など)
百日咳の治療は、主に薬物療法と対症療法が行われます。
- 薬物療法: 百日咳菌に対する抗菌薬(マクロライド系など)が用いられます。早期に投与することで、菌の排出期間を短縮し、周囲への感染拡大を防ぐ効果が期待できます。ただし、症状が出てから時間が経つと、抗菌薬の効果は限定的になります。
- 対症療法: 咳止めや気管支拡張薬は、症状の緩和にはあまり効果がないとされています。安静を保ち、水分を十分に摂取することが重要です。特に乳幼児の場合は、呼吸状態が悪化することがあるため、入院して酸素投与や呼吸管理が必要になることがあります。
- 生活習慣: 刺激の少ない環境で安静に過ごすことが大切です。咳が出やすい冷たい空気や乾燥を避け、加湿を行うと良いでしょう。食事は、少量ずつ、消化の良いものを摂取するように心がけます。
※手術による治療は、通常行われません。
🎵予防・対策(患者自身ができること、生活の中で気を付けること)
百日咳の最も有効な予防法は、ワクチン接種です。
日本では、DPT-IPVワクチン(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオの四種混合ワクチン)として定期接種が行われています。追加接種も推奨されていますので、接種スケジュールを確認し、適切にワクチンを受けることが重要です。
患者自身ができることとしては、以下の点が挙げられます。
- 早期の診断と治療: 咳が長引く場合は、早めに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。
- 感染拡大の防止: 咳やくしゃみをする際は、ティッシュやハンカチで口や鼻を覆い、使用済みのティッシュはすぐにゴミ箱に捨てましょう。咳をしているときは、可能な限り人との接触を避け、外出を控えるようにしましょう。
- 手洗いの徹底: 帰宅後や食事前など、こまめな手洗いを心がけましょう。アルコール消毒も有効です。
- 家族や周囲への配慮: 家族や職場の同僚など、周囲の人に百日咳と診断されたことを伝え、感染予防に協力してもらいましょう。特に、ワクチン接種をしていない乳幼児や免疫力の低い人がいる場合は注意が必要です。
🎵まとめ
百日咳は、百日咳菌による感染力の強い呼吸器感染症であり、特徴的な激しい咳が長く続く病気です。カタル期、痙咳期、回復期と経過が変化し、特に痙咳期の激しい咳込みが特徴的です。診断には、臨床症状に加え、細菌学的検査や血清学的検査が行われます。治療は主に抗菌薬による薬物療法と、安静や水分補給などの対症療法が中心となります。最も重要な予防法はワクチン接種であり、患者自身も早期診断・治療、感染拡大防止のための咳エチケットや手洗いの徹底が求められます。

健康や病気について学べるクリニック
東京メトロ東西線葛西駅より徒歩5分 葛西内科皮膚科クリニック
【医療法人社団 俊爽会 理事長 小林俊一 監修】